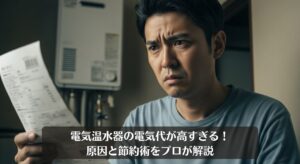インターホンと電話機を連動!交換・価格・子機の疑問を解説

- 1. インターホンと電話機を連動する基本とメリット
- 1.1. メリットと必要性
- 1.2. アダプター接続は自分でできる?
- 1.2.1. DIYが可能なケース
- 1.2.2. 専門業者への依頼が必要なケース
- 1.3. 便利な内線通話とは?
- 1.4. 電話機型や一体型への交換について
- 1.5. 主要メーカーのパナソニック・NTT・アイホン
- 1.5.1. パナソニック(Panasonic)
- 1.5.2. NTT
- 1.5.3. アイホン(Aiphone)
- 2. インターホンの電話機連動を導入前に知るべき事
- 2.1. 親機の品番と対応表で互換性を確認
- 2.1.1. 品番の確認方法
- 2.1.2. 対応表でのチェック
- 2.2. マンションでの設置工事と価格の相場
- 2.2.1. 管理規約の確認が最優先
- 2.2.2. 工事の価格相場
- 2.3. 子機は他メーカーでも使えますか?
- 2.4. ワイヤレス子機を増設できますか?
- 2.5. 横浜近郊のインターホン工事、私たちにお任せください!
- 2.6. まとめ:インターホンと電話機を連動する最適な方法
「インターホンと電話機を連動させたいけれど、何から手をつければいいのだろう?」と、お悩みではありませんか。
インターホンと電話機の連動は、日々の暮らしやビジネスシーンを格段に便利にしてくれますが、その一方で多くの疑問も浮かび上がります。
例えば、連動させる具体的なメリットや必要性、自分で交換できるのか、マンションで設置する場合の価格相場など、気になる点は多いはずです。
また、アダプターを使った接続方法や、今使っている親機との対応表や互換性の確認も欠かせません。電話機型を選ぶべきか、思い切って一体型へ交換するべきか、という選択肢もあります。
さらに、「子機を増設できますか?」あるいは「子機は他メーカーでも使えますか?」といった細かい疑問や、そもそも内線通話とは何か、パナソニックやNTT、アイホンといった主要メーカーごとにどのような違いがあるのかなど、知りたいことは尽きないでしょう。
この記事では、ドアホンと電話機の連動に関するこれらのあらゆる疑問を一つひとつ丁寧に解き明かし、あなたの環境に最適なシステム選びをサポートします。
記事のポイント
- インターホンと電話機を連動させるメリットと仕組み
- 主要メーカーごとの特徴と製品の互換性
- DIYでの交換や業者依頼時の価格相場
- 子機の増設や他メーカー製品が使えるかの疑問
インターホンと電話機を連動する基本とメリット
- メリットと必要性
- アダプター接続は自分でできる?
- 便利な内線通話とは?
- 電話機型や一体型への交換について
- 主要メーカーのパナソニック・NTT・アイホン
メリットと必要性
インターホンと電話機を連動させる最大のメリットは、来客応対の利便性が飛躍的に向上することにあります。
ご家庭であれば、わざわざ親機のある場所まで行かなくても、リビングや書斎、2階の部屋など、普段使っている電話機の子機で来客応対ができます。
これにより、手が離せない家事の途中や、体調がすぐれない時でもスムーズに対応が可能になるのです。ビジネスシーンにおける必要性はさらに高まります。
オフィスや店舗では、スタッフが受付から離れた場所で作業していることも少なくありません。
連動システムがあれば、各自のデスクに座ったままビジネスフォンで来客対応ができるため、業務を中断する時間を最小限に抑え、生産性の向上に直接つながります。
機種によっては電子錠と連携し、自席からドアの解錠操作も可能です。一方で、デメリットや注意点も存在します。
まず、導入には初期費用がかかります。対応するインターホンと電話機を揃える必要があり、場合によっては専門業者による工事費も発生します。
また、全ての機種が連動できるわけではないため、購入前には互換性の確認が不可欠です。
これらの点を踏まえ、自身の生活スタイルや業務内容にとって、利便性向上の価値がコストを上回るかどうかを判断することが大切になります。

アダプター接続は自分でできる?
インターホンと電話機の連動を実現する方法の一つに、ドアホンアダプターを介した接続があります。
この方法は、既存の設備を活用できる可能性がある一方で、「自分で設置できるのか」という疑問がよく聞かれます。この問いに対する答えは、「設置環境や製品の電源方式による」となります。
ドアホンアダプター自体は、インターホンからの信号を電話機で受信できる形式に変換するための中継器のようなものです。
このアダプターの設置や配線作業がDIYで可能かどうかは、インターホン親機の電源の取り方が大きな分かれ目です。
DIYが可能なケース
インターホンの親機が、コンセントに電源コードを差し込む「電源コード式」の場合、多くは特別な資格がなくても交換や設置が可能です。
ドアホンアダプターへの配線も、説明書に従ってケーブルを接続する作業が中心となるため、DIYに慣れている方であれば自分で挑戦できる可能性があります。
専門業者への依頼が必要なケース
一方、親機の配線が壁の中の電源線に直接接続されている「電源直結式」の場合は注意が必要です。
この配線工事には「電気工事士」の国家資格が法律で義務付けられています。資格を持たない方が作業を行うことは法令違反となるだけでなく、火災や感電といった重大な事故につながる危険があります。
このため、電源直結式のインターホンにアダプターを接続する場合は、必ず専門の業者に依頼しなければなりません。
したがって、アダプター接続を検討する際は、まず自宅やオフィスのインターホンの電源方式を確認することが第一歩です。
安全かつ確実に連動システムを導入するため、少しでも不安があれば無理をせずプロに相談することをおすすめします。

便利な内線通話とは?
内線通話とは、同じ建物内や同一の電話システムに接続された電話機同士で、外線(公衆電話網)を使わずに無料で通話できる機能のことを指します。
オフィスでは部署間の連絡に、家庭では部屋間のコミュニケーションに利用されるのが一般的です。
この内線通話機能が、インターホンと電話機の連動において非常に便利な役割を果たします。
インターホンとビジネスフォンや家庭用電話機を連携させると、インターホンの玄関子機や室内子機が、電話システム全体の一つの「内線端末」として認識されるようになります。
これにより、具体的には以下のようなことが可能になります。
- 電話機からインターホンへの発信
来客がないときでも、電話機から特定の内線番号(インターホンに割り当てられた番号)をダイヤルして、玄関先の様子を音声で確認したり、玄関付近にいる家族やスタッフに呼びかけたりできます。 - インターホンからの呼び出しを複数の電話機で受信
来客が玄関子機のボタンを押すと、インターホンの親機だけでなく、連携している全ての電話機や子機が一斉に内線着信として鳴動します。これにより、どこにいても来客に気づきやすくなります。 - インターホンと電話機での相互通話
インターホンを電話システムに組み込むことで、電話機の子機がインターホンの応答機として、逆にインターホンの子機が電話の内線子機として機能するモデルもあります。
このように、内線通話は単なる無料通話機能にとどまりません。インターホンと電話機を一つのコミュニケーションシステムとして統合し、家やオフィス全体の利便性と応答性を高めるための基盤となる技術なのです。

電話機型や一体型への交換について
インターホンとの連動を考える際、電話機を「電話機型」のまま使うか、「一体型」に交換するかは一つの選択ポイントです。どちらが良いかは、設置スペースや求める機能、デザインの好みによって異なります。
「電話機型」とは、現在お使いの電話機とインターホンを、前述のドアホンアダプターやワイヤレス機能(DECT準拠方式など)で接続する構成を指します。
最大のメリットは、愛着のある電話機や高機能なFAX電話機などをそのまま活用できる点です。
電話機は電話機、インターホンはインターホンとして、それぞれの機器が独立しているため、片方が故障しても個別に入れ替えができます。
一方、「一体型」は、インターホンのモニター親機に電話機能が内蔵された製品です。モニター画面で来客の顔を確認し、そのまま受話器やハンズフリー機能で通話できます。
このタイプの利点は、省スペースであることと、デザインに統一感が出ることです。壁面に設置する機器が一つで済むため、見た目がすっきりします。
どちらのタイプを選ぶべきか、以下の表でメリットとデメリットを比較してみましょう。
| タイプ | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 電話機型 | ・既存の電話機やFAXを活用できる ・機器を個別に交換できる ・導入コストを抑えられる場合がある | ・設置スペースが余分に必要 ・対応するアダプターなどが必要 ・配線が複雑になることがある |
| 一体型 | ・省スペースで見た目がすっきりする ・一つの機器で操作が完結する ・デザインの統一感がある | ・電話機能が比較的シンプル ・故障した場合、全体の交換が必要になる可能性がある ・製品の選択肢が限られる |
オフィスでビジネスフォンと連携させる場合は、基本的に「電話機型」の構成となります。
この場合、インターホンは主装置内の専用ユニットを介して各ビジネスフォンと接続され、システム全体で来客応対が可能になります。
以上の点を踏まえると、自分の使い方や設置環境をよく考え、どちらのタイプがより適しているかを判断することが交換を成功させる鍵となります。

主要メーカーのパナソニック・NTT・アイホン
インターホンと電話機の連動システムを選ぶ上で、主要メーカーであるパナソニック、NTT、アイホンの特徴を理解しておくことは非常に有益です。
各社はそれぞれ異なる強みを持ち、提供する製品群も多岐にわたります。
パナソニック(Panasonic)
家庭用インターホンおよび電話機の分野で、非常に高いシェアを誇るメーカーです。
パナソニックの最大の特徴は、「外でもドアホン」や「どこでもドアホン」といったシリーズで確立された、自社製品同士の強力な連携エコシステムにあります。
特に「DECT準-拠方式」という1.9GHz帯のデジタルコードレス規格を積極的に採用しており、対応するインターホン親機と電話機・FAX親機をワイヤレスで接続できるモデルが豊富です。
これにより、配線を気にせず電話子機や専用スマホアプリで来客応答やモニター確認が可能になります。
NTT
NTTは、特にビジネスフォンの分野で長年の実績と高い信頼性を持っています。
官公庁や大企業で広く採用されている「αシリーズ」などのビジネスフォンシステムは、ドアホン連携機能も標準的にサポートしています。
NTT製ビジネスフォン(例:αNXシリーズ)はドアホンユニット接続により来客応対・電気錠解錠に加え、ドアホン着信の外線転送も標準機能で可能です(映像転送は対応機のみ)。
家庭用というよりは、信頼性と拡張性が求められるビジネス環境での導入に適しています。
アイホン(Aiphone)
アイホンは、インターホン専門メーカーとして業界をリードする存在です。
戸建て住宅向けから、集合住宅のオートロックシステム、病院や工場向けの特殊なインターホンまで、幅広い製品ラインナップを持っています。
セキュリティ機能を重視した製品開発に強みがあり、高画質なカメラや録画機能、各種センサーとの連携機能を備えたモデルが多数あります。
近年は、既存のLAN配線を活用してシステムを構築するフルIPインターホンシステム「IXシステム」など、大規模施設や高度なセキュリティが求められる場所向けのソリューションにも力を入れています。
専門メーカーならではの堅牢性と信頼性が魅力です。
このように、メーカーごとに得意とする領域や技術的なアプローチが異なります。
パナソニックは家庭での使いやすさ、NTTはビジネスでの信頼性、アイホンはセキュリティと専門性、という大まかな特徴を念頭に置いて製品を比較検討すると、自分のニーズに合ったメーカーが見つかりやすくなります。

インターホンの電話機連動を導入前に知るべき事
- 親機の品番と対応表で互換性を確認
- マンションでの設置工事と価格の相場
- 子機は他メーカーでも使えますか?
- ワイヤレス子機を増設できますか?
- まとめ:インターホンと電話機を連動する最適な方法
親機の品番と対応表で互換性を確認
インターホンと電話機の連動システムを導入する上で、最も注意すべき点が「互換性」の確認です。
デザインや価格だけで選んでしまうと、いざ接続しようとした際に「うまく動作しない」「一部の機能しか使えない」といった失敗につながりかねません。
これを避けるためには、購入前に必ず親機の品番を確認し、メーカーが公開している対応表で互換性をチェックする作業が不可欠です。
品番の確認方法
まず、現在使用している、あるいは購入を検討しているインターホンと電話機の「親機」の品番を正確に把握します。
品番は通常、機器本体の正面や側面、底面に貼られたシールに記載されています。例えば、パナソニック製の電話機であれば「VE-GD78-W」のように記載されていることがあります。
この場合、「-W」は色を表す記号なので、対応表で探す際は「VE-GD78」までが製品の型番となります。
セット品番(例:VE-GD78DL)と親機の単体品番が異なる場合もあるため、親機本体の表記を確認することが確実です。
対応表でのチェック
次に、各メーカーの公式ウェブサイトにアクセスし、「サポート」「よくあるご質問」「接続確認済み機器」といったページから、ドアホン連携の対応表を探します。
この対応表には、どのインターホンとどの電話機が接続可能か、また、どのような機能(音声通話、映像表示、ワイヤレス接続など)が使えるかが一覧で示されています。
自分の持っている、または購入予定の親機の品番がリストに記載されているか、そして希望する連携機能がサポートされているかを丁寧に確認してください。
特に中古品を購入する場合や、インターホンと電話機を別々の時期に購入した場合は、この互換性チェックを怠ると後で後悔することになります。
少し手間に感じるかもしれませんが、確実な連動を実現するための最も重要なステップであると認識し、慎重に確認作業を行いましょう。

マンションでの設置工事と価格の相場
マンションでインターホンと電話機の連動を検討する場合、戸建て住宅とは異なる注意点があります。特に、工事の可否と費用については、事前にしっかりと確認しておく必要があります。
管理規約の確認が最優先
マンションにおいて最も大切なのは、管理組合が定める「管理規約」を確認することです。
インターホンの設備は、個人の住戸内(専有部分)で完結している場合と、エントランスのオートロックなどマンション全体のシステム(共用部分)と連動している場合があります。
専有部分のみのインターホン(玄関子機と室内の親機のみ)であれば、交換や連動工事は比較的自由に行えることが多いです。
しかし、共用部分の設備に手を入れる工事は、原則として個人で勝手に行うことはできません。
オートロックと連動しているインターホンを交換したい場合は、必ず事前に管理組合や管理会社に相談し、許可を得る必要があります。
許可なく工事を行うと、規約違反になったり、マンション全体のシステムに不具合を生じさせたりする可能性があります。
工事の価格相場
インターホン交換や連動工事の価格は、工事の内容によって大きく変動します。
- 既存配線を流用して機器を交換する場合
最もシンプルな工事で、機器本体を除く取付工事費は13,000~20,000円前後が相場です。 - 新規で配線工事が必要な場合
壁内に新たに配線を通したり、電源を確保したりする工事が必要になると、費用は3万円~8万円以上に上がることがあります。 - オートロック連動の場合
前述の通り、これは大規模な工事になる可能性があり、費用はケースバイケースです。個人で依頼するのではなく、マンション全体での修繕計画として行われるのが一般的です。
いずれの場合も、正確な費用を知るためには、複数の専門業者から見積もりを取ることを強く推奨します。
業者によって技術料や出張費が異なるため、相見積もりを取ることで適正な価格を把握でき、信頼できる業者を選ぶことにもつながります。

子機は他メーカーでも使えますか?
インターホンや電話機を買い替える際に、「今使っている子機を、新しい別のメーカーの親機でも使えないだろうか」と考える方は少なくありません。
コストを抑えたいという気持ちは理解できますが、この問いに対する答えは、残念ながら「原則として使用できない」となります。
その理由は、メーカーごとに採用している通信方式や信号の仕様が異なるためです。
特に家庭用のコードレス電話機やインターホン子機で広く使われている「DECT準拠方式」というデジタル通信規格があります。
この規格は、Wi-Fi(2.4GHz帯)との電波干渉が起きにくいというメリットがありますが、「DECT準拠方式」の製品同士でも、メーカーが異なる場合は GAP対応機を除き基本的にペアリングできません。
これは、基本的な通信プロトコルは規格で定められていても、セキュリティのための暗号化処理や、メーカー独自の付加機能を実現するための信号などが独自仕様となっているためです。
他メーカーの親機に子機を登録しようとしても、親機が子機を正しく認識できず、ペアリング(接続設定)を完了させることができません。
したがって、インターホンや電話機の子機は、必ず親機と同じメーカーの対応製品を使用する必要があります。
一部の例外的な製品を除き、他メーカーの子機を流用することはできないと考えるのが賢明です。
もし対応していない子機を無理に接続しようとすると、故障の原因にもなりかねません。子機を増やす、あるいは交換する場合は、必ずメーカーの対応表を確認し、指定された純正品を選ぶようにしてください。

ワイヤレス子機を増設できますか?
「リビングの親機まで行くのが遠い」「2階の部屋にも応答できる子機が欲しい」といったニーズに応えるため、ワイヤレス子機の増設は非常に有効な手段です。
多くの家庭用電話機やインターホンシステムでは、子機の増設に対応しています。
ただし、増設が可能かどうか、また何台まで増やせるかは、お使いの「親機」の仕様によって決まります。
まず確認すべきなのは、親機が子機の増設に対応している機種かどうかです。製品の取扱説明書やメーカーのウェブサイトで仕様を確認すれば、増設の可否が分かります。
次に見るべき点は、増設できる子機の数は4~6台が主流ですが、最新ビジネスフォンや一部家庭用機では最大8台まで対応するモデルもあります。
例えば、購入時に親機と子機1台がセットになっている製品で、上限が6台であれば、あと5台まで子機を買い足して増設できるということになります。
増設用のワイヤレス子機は、家電量販店やオンラインストアで別途購入できます。この際も、前述の通り、必ず親機と同じメーカーの対応品番の子機を選ぶ必要があります。
子機の増設手順は、通常、新しい子機を充電台にセットして電源を入れ、親機側を登録モードにしてから、子機側で特定のボタンを操作するといった簡単なものです。詳しい手順は必ず取扱説明書で確認してください。
このように、対応機種を選べばワイヤレス子機の増設は比較的簡単に行えます。家のどこにいても来客や電話に応答できる快適な環境を整えるために、子機の増設を検討してみてはいかがでしょうか。

横浜近郊のインターホン工事、私たちにお任せください!
ここまでインターホンの連動について詳しく解説してきましたが、「うちの場合はどうなんだろう?」「やっぱり配線工事は自分では不安だな…」と感じた方もいらっしゃるかもしれませんね。
特に、壁の中の配線を扱う「電源直結式」の工事は、法律で定められた電気工事士の資格が必須です。安全と確実性を考えるなら、無理せずプロに任せるのが一番の近道です。
実は、この記事を書いている私たち「横浜電気工事レスキュー」も、インターホンの交換から設置まで、ばっちり対応しております。
「どの機種が自宅に合うの?」といったご相談から、お見積り、そして実際の取り付けまで、資格を持ったプロのスタッフが丁寧に対応させていただきます。横浜市や川崎市、その周辺エリアでしたら、喜んでお伺いします。
まとめ:インターホンと電話機を連動する最適な方法
この記事では、インターホンと電話機の連動に関する様々な側面を解説してきました。
最適なシステムを選ぶためには、多くの要素を総合的に判断する必要があります。最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。
- インターホンと電話機の連動で来客対応が便利になる
- ビジネス用途では業務効率化、家庭では防犯性向上が期待できる
- 連動には対応機種同士の組み合わせが必須
- パナソニック、NTT、アイホンなどメーカーごとに特徴がある
- 連携方法はドアホンアダプターやワイヤレスDECT方式など
- 電源直結式の配線工事には、電気工事士法第3条により有資格者のみが施工可能と定められている
- 自分で交換できるのは電源コード式や乾電池式が中心
- 電話機型と一体型は設置スペースや機能で選ぶ
- 導入前に親機の品番で対応表や互換性を必ず確認する
- 子機の増設は親機の登録上限台数まで可能
- 他メーカーの子機は通信方式が違うため原則使用できない
- マンションでの工事は管理規約の確認を先に行う
- 工事費用は既存配線の有無で大きく変動する
- ビジネスフォン連携には主装置や専用ユニットが必要になる
- 機能と予算、設置環境を総合的に見て最適なシステムを選ぶ