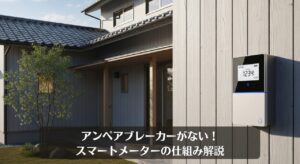吹き抜けシーリングファン工事費用|相場と業者選びの全知識

吹き抜けのあるおしゃれなリビング。
その開放感とデザイン性の高さから、多くの人が憧れる空間ですが、その一方で「夏は2階が蒸し風呂のように暑く、冬は1階の足元が凍えるほど寒い」といった、深刻な温度差の問題を抱えているご家庭も少なくありません。
その解決策としてシーリングファンを検討する中で、「吹き抜けのシーリングファン工事費用は一体いくらかかるのだろう?」という大きな疑問に突き当たる方は多いでしょう。
単純な照明交換費用とは異なり、高所取り付け工事には特有の費用が発生します。
また、新築ではなく後付けで配線工事が必要な場合や、戸建てかマンションかといった住環境によっても、費用や注意点は大きく変わるものです。
そもそも本当に必要なのか、いらないと思って付けずに後悔しないか、という根本的な悩みから、信頼できる業者の選び方、さらには自分でDIYできるのかという疑問まで、考えるべきことは多岐にわたります。
この記事では、ヤマダ電機やエディオン、ケーズデンキのような家電量販店と、ヘーベルハウスや三井ホーム、パナソニックのようなハウスメーカー系業者に依頼する場合の違いを解説します。
さらに、設置後のメンテナンスを劇的に楽にする昇降機後付けの可能性、つけっぱなしにした場合の電気代、そして補助金や保険の適用可否についても詳しく掘り下げます。
吹き抜けのシーリングファン設置に関するあなたの全ての疑問に、専門的な知見から徹底的にお答えしていきます。
記事のポイント
- 吹き抜けへのシーリングファン設置にかかる費用の総額がわかる
- 信頼できる業者の選び方と悪徳業者を避けるポイントが理解できる
- 後付けやDIYの可否と、それに伴う具体的なリスクが明確になる
- 設置後のメンテナンス方法やランニングコスト(電気代)の知識が身につく
- 1. 吹き抜けシーリングファンの工事費用の内訳と相場
- 1.1. 高所取り付け工事で料金は変わる
- 1.1.1. 費用の最重要ポイント:足場代の内訳を確認する
- 1.2. 既存の照明交換費用との違い
- 1.3. そもそも必要?いらない?後悔しない判断基準
- 1.3.1. 必要なケース
- 1.3.2. 主なメリット
- 1.3.3. いらない可能性のあるケース
- 1.3.4. デメリットと注意点
- 1.3.5. ランニングコスト(電気代)
- 1.4. 信頼できる専門業者の選び方
- 1.4.1. 1. 吹き抜けへの豊富な設置実績と専門知識
- 1.4.2. 2. 全ての項目が含まれた詳細な見積もり
- 1.4.3. 3. 必要な資格の保有と損害賠償保険への加入
- 1.4.4. 4. コミュニケーション能力と提案力
- 1.5. ヤマダ電機・エディオン・ケーズデンキでの依頼
- 1.5.1. 吹き抜けのような特殊工事への対応力
- 1.6. 戸建てやマンションでの注意点
- 1.6.1. 戸建ての場合:最重要課題は「天井の強度」
- 1.6.2. マンションの場合:確認すべきは「管理規約」と「天井の構造」
- 2. 依頼前に!吹き抜けシーリングファンの工事費用と注意点
- 2.1. 後付け配線が必要になるケース
- 2.1.1. 配線工事に伴う高額な追加費用と内装工事のリスク
- 2.2. ヘーベルハウス・パナソニック・リクシルへの依頼
- 2.3. 自分でDIYする場合のリスクと法的注意点
- 2.3.1. 1. 身体へのリスク(落下・転落事故)
- 2.3.2. 2. 家屋へのリスク(設置不良による故障・落下)
- 2.3.3. 3. 法的なリスク(無資格工事による違法性と保険の問題)
- 2.4. 掃除のための昇降機後付けという選択肢
- 2.4.1. 昇降機は後付けも可能!長期的な視点で検討を
- 2.5. 補助金や保険は適用されるのか
- 2.5.1. 補助金について:直接的な制度はほぼ皆無
- 2.5.2. 火災保険について:適用は災害による損害時のみ
- 2.6. 吹き抜けシーリングファンの工事費用:総まとめ
吹き抜けシーリングファンの工事費用の内訳と相場
- 高所取り付け工事で料金は変わる
- 既存の照明交換費用との違い
- そもそも必要?いらない?後悔しない判断基準
- 信頼できる専門業者の選び方
- ヤマダ電機・エディオン・ケーズデンキでの依頼
- 戸建てやマンションでの注意点
高所取り付け工事で料金は変わる
一般的な天井高(約2.4m)で、既存の配線器具がある前提のシーリングファン取付工賃は、家電量販店の掲示例で5,500円~が目安です。
しかし、床から天井までが3mを超えるような吹き抜けの場合、この基本工賃に加えて「高所作業費」が必ず発生します。
これは、2mを超える長尺の脚立や、安全性を確保するための移動式の足場(ローリングタワー)の設置が必要となり、作業の難易度と危険性が格段に増すためです。
多くの量販店では「天井高3mを超えると高所扱い」とされ、追加費用が別途発生します。
天井高が5mを超える場合は、移動式足場(ローリングタワー)などを設置する必要があり、設置規模や作業日数によって3万円台~10万円超と幅があります。
費用の最重要ポイント:足場代の内訳を確認する
吹き抜けの工事費用は、「基本工賃」+「高所作業費」+「足場代」の合計で考える必要があります。
特に総額を大きく押し上げるのが足場代です。シーリングファン専門店の中には、自社で移動式足場を保有しており、足場代を比較的安価に設定している場合があります。
一方で、一般的な電気工事業者は足場を外部からレンタルするため、その費用がそのまま上乗せされ高額になりがちです。
見積もり時には必ず足場の有無と、その費用がレンタル料なのか、自社保有によるものなのかまで確認しましょう。
このように、天井の高さが1m違うだけで費用が数万円単位で変動するため、単純な設置料金だけを見て判断するのは非常に危険です。
複数の業者から見積もりを取り、高所作業に関する費用の内訳(特に足場代)を詳細に比較することが、適正価格で高品質な工事を行うための絶対条件となります。

既存の照明交換費用との違い
シーリングファンの設置を、リビングのシーリングライトを交換するような一般的な「照明交換費用」と同じ感覚で考えていると、見積もりを見てその金額の差に驚くことが少なくありません。
両者の費用の違いは、単なる作業の手間だけでなく、「作業の専門性」「重量」「安全性確保」という3つの大きな要素に起因します。
通常の照明器具の交換は、既存の配線器具(引掛シーリング)にアダプターを取り付け、数キロ程度の軽い本体をはめ込むだけの簡単な作業が多く、DIYで行う人も少なくありません。
業者に依頼しても1万円以下で済むことがほとんどです。
しかし、シーリングファンは本体が重く、軽量なものでも5kg、照明付きの大型モデルでは10kg以上になります。
ファンブレード(羽根)の一枚一枚を正確に取り付け、全体のバランスを取りながら配線接続を行うなど、工程が格段に複雑になります。
そして最も決定的な違いが、天井の強度確認と補強工事の必要性です。
照明器具と比べてはるかに重いシーリングファンの重量と、回転時に発生する継続的な振動に天井が耐えられるかどうかが、安全性を左右する最大のポイントです。
特に築年数が経過した住宅や、補強が考慮されていない天井の場合、落下の危険があるため「天井補強工事」が必須となります。
この補強工事は、天井裏にアクセスして梁や根太に厚い合板などの下地を新たに追加する大掛かりな作業となり、費用は6万円~20万円程度の掲示例が多く、条件によっては10万円超となるケースもあります。
以下の表で、両者の違いを具体的に比較してみましょう。
| 項目 | 一般的な照明交換 | シーリングファン設置(吹き抜け) |
|---|---|---|
| 平均重量 | 1~3kg | 5~10kg以上 |
| 作業内容 | 既存器具への接続が主 | 本体組立、バランス調整、強度確認など複雑 |
| 天井補強工事 | ほぼ不要 | 必須の場合が多く、高額になりやすい |
| 高所作業/足場 | 不要な場合が多い | ほぼ必須(費用は高さによる) |
| 合計目安 | 3,000円~10,000円 | 50,000円~300,000円超 |
このように、シーリングファンの設置は単なる「交換」ではなく、構造力学や電気工事の知識を要する「専門工事」と捉え、安易に考えずに専門家へ相談することが重要です。

そもそも必要?いらない?後悔しない判断基準
高額な工事費用がかかる可能性のあるシーリングファンですが、「本当に我が家に必要なのだろうか?」と設置を迷う方も多いでしょう。
デザイン性だけで設置してしまい、「思ったより効果がなかった」「掃除が大変で後悔…」といった事態は避けたいものです。
そのためにも、設置のメリットとデメリットを正しく理解し、ご自身の住まいとライフスタイルに本当に必要かどうかを冷静に判断することが大切です。
必要なケース
シーリングファンの最大の役割は、物理法則に基づいた「空気の循環による快適性の向上」です。
暖かい空気は軽く上に、冷たい空気は重く下に溜まる「温度成層」という現象は、特に上下の空間が広い吹き抜けでは顕著に現れます。
その結果、夏はエアコンの冷気が届かない2階が蒸し暑く、冬は暖房の熱が昇ってしまい1階の足元が寒い、という典型的な問題が発生します。
シーリングファンはこの空気を強制的に攪拌し、室内全体の温度を均一にすることで、冷暖房の効率を劇的に向上させます。
主なメリット
- 冷暖房効率の向上
- エアコンの設定温度を夏は1~2℃上げ、冬は1~2℃下げても快適さが保たれ、結果として電気代の大幅な節約につながります。
- 快適性の向上
- 室内の温度ムラがなくなり、家のどこにいても心地よく過ごせるようになります。特に冬場の足元の冷えが大きく改善されます。
- 空気のよどみ解消
- 室内の空気が常に対流することで、湿気や臭いがこもりにくくなり、カビや結露の防止にも繋がります。
- 補助的な効果
- 洗濯物の部屋干しが格段に乾きやすくなる、観葉植物の生育環境が良くなるなどの副次的なメリットもあります。
- デザイン性
- 空間のシンボルとなり、インテリアのアクセントとしてリビングをおしゃれに演出します。
いらない可能性のあるケース
一方で、ライフスタイルや建物の性能によっては、デメリットが上回る可能性もあります。
最も大きな課題は「掃除・メンテナンスの手間とコスト」です。高所にあり、しかも凹凸のある羽根の上にはホコリが驚くほど溜まります。
放置すれば、運転時にアレルゲンを含んだホコリを部屋中にまき散らすことになりかねません。自分で掃除するには危険が伴い、業者に依頼すれば数万円の費用が定期的に発生します。
デメリットと注意点
- メンテナンス
- 前述の通り、掃除が非常に大変です。電動昇降機を設置しない限り、大きな負担となります。
- 騒音
- DCモーター搭載の静音モデルが増えていますが、それでも風切り音やモーターの動作音が発生します。音に敏感な方は、寝室近くの吹き抜けへの設置は慎重に検討すべきです。
- 初期費用
- 本体価格に加えて高額な工事費がかかるため、初期投資は決して安くありません。
- 圧迫感
- 天井高や部屋の広さに対して大きすぎるモデルを選ぶと、圧迫感を感じることがあります。
- 高気密・高断熱住宅での必要性
- 近年、住宅の高気密・高断熱化が進んでいます。第一種換気システム(全熱交換器)などを導入した最新の高性能住宅では、そもそも家全体の温度ムラが発生しにくく、空気も計画的に循環しています。
- このような住宅では、シーリングファンの費用対効果は限定的になる可能性があります。
ランニングコスト(電気代)
- DCモーター
- 省エネ性能と静音性に優れ、細かな風量調整が可能です。消費電力は最大でも20W〜30W程度。
- ACモーター
- 構造がシンプルで本体価格が安い傾向にありますが、消費電力は40W〜60W程度とDCモーターの約2倍になります。
つけっぱなしにしても電気代の負担は比較的小さいですが、初期費用とランニングコストのバランスを考えてモーターの種類を選ぶことが重要です。
最終的には、これらのメリット・デメリットを天秤にかけ、ご自身のライフスタイル、建物の性能、そして予算を総合的に考慮して、後悔のない判断を下しましょう。

信頼できる専門業者の選び方
吹き抜けへのシーリングファン設置は、電気工事と建築知識の両方が求められる、専門性の高い工事です。工事の成否は業者選びにかかっていると言っても過言ではありません。
安全かつ美しく、そして適正価格で設置するためには、以下のポイントを押さえて信頼できる業者を慎重に選ぶ必要があります。
業者を選ぶ際には、最低でも以下の4つのポイントを必ず確認しましょう。
1. 吹き抜けへの豊富な設置実績と専門知識
まず最も重要なのが、その業者が吹き抜けへのシーリングファン設置実績が豊富かどうかを確認することです。
業者の公式サイトで施工事例集をチェックし、自分と似たような条件(天井高、勾配天井など)の吹き抜けに設置した経験が多数あるかを確認しましょう。
実績豊富な業者は、高所作業の安全管理、最適な足場の選定と設置、天井構造に合わせた確実な補強方法といった専門的なノウハウを蓄積しています。
問い合わせの際に、「天井高5mの勾配天井なのですが、どのような足場を組んで、どうやって補強しますか?」といった具体的な質問を投げかけてみましょう。
その回答が明確で、専門用語を交えつつも分かりやすく説明してくれる業者は信頼できる可能性が高いです。
2. 全ての項目が含まれた詳細な見積もり
「工事一式 〇〇円」といった、内訳が不明瞭な大雑把な見積もりを提示する業者は絶対に避けましょう。
信頼できる優良業者は、必ず誰が見ても理解できるよう、項目ごとに単価と数量が明記された詳細な見積もりを提出します。
これにより、何にいくらかかるのかが明確になり、後から不当な追加請求をされるリスクを防げます。
【見積もりで最低限確認すべき項目リスト】
- シーリングファン本体価格(施主支給の場合は不要)
- 基本組立・設置工賃
- 高所作業費(天井高〇mの場合、など条件明記)
- 足場設置・解体費用(足場の種類・規模も)
- 天井下地補強工事費(工法・使用材料も)
- 電気配線工事費(新規・延長など)
- 既存照明器具の撤去・処分費
- 出張費・諸経費
これらの項目が全て記載されているか、そして不明な点はないかを徹底的に確認してください。
3. 必要な資格の保有と損害賠償保険への加入
前述の通り、配線工事を伴う作業には「第二種電気工事士」以上の国家資格が法律で義務付けられています。
無資格での工事は違法であり、火災や漏電という重大な事故につながるため、必ず資格者証の提示を求めるなどして有資格者が在籍しているかを確認しましょう。
また、万が一の物損事故や人身事故に備えて、請負業者賠償責任保険などの損害賠償保険に加入しているかも、企業の信頼性を測る上で非常に重要なチェックポイントです。
4. コミュニケーション能力と提案力
最終的には、担当者との相性も大切です。こちらの要望や不安を親身に聞いてくれるか、専門的な内容を分かりやすく説明してくれるかは重要なポイントです。
その上で、現状を踏まえた最適な機種や設置方法を積極的に提案してくれるか、といったコミュニケーション能力も判断基準に加えましょう。
最も確実な方法は、最低3社から相見積もりを取ることです。
費用が安いというだけで決めるのではなく、上記のポイントを総合的に比較検討し、最も信頼でき、安心して大切な家の工事を任せられる業者を見つけることが、成功への最短ルートです。

ヤマダ電機・エディオン・ケーズデンキでの依頼
シーリングファンの購入先として最も身近な存在である、ヤマダ電機、エディオン、ケーズデンキといった大手家電量販店でも、製品の購入と同時に設置工事を依頼することが可能です。
その手軽さから、最初の相談先として検討する方も多いでしょう。
家電量販店に依頼する最大のメリットは、やはりその利便性にあります。豊富な展示品の中から実物を見て製品を選び、その場で工事の申し込みまで完結できるワンストップサービスは大きな魅力です。
また、購入金額に応じたポイントが付与されるため、実質的な負担を軽減できる場合もあります。
ただし、その手軽さの裏にある注意点も理解しておく必要があります。
家電量販店が自社の社員で工事を行うわけではなく、業務提携している地域の下請けの電気工事業者が実際の作業を担当する仕組みです。
そのため、どの業者が担当になるかを選ぶことはできず、担当する業者によって技術力や対応の質にばらつきが生じる可能性があります。
吹き抜けのような特殊工事への対応力
最も注意すべき点は、家電量販店の標準的な取り付け工事は、あくまで一般的な天井高(2.4m前後)で、かつ既存の配線器具がある場合を想定しているということです。
吹き抜けのような高所作業や、天井補強・新規配線といった特殊な工事には、原則として対応していなかったり、対応可能であっても専門業者に依頼するより高額な追加料金が発生したりするケースがほとんどです。
相談時には、自宅の吹き抜けの状況(正確な天井高、勾配の有無、下地の有無、電源の有無など)を写真や図面で正確に伝えた上で、以下の点を確認することが不可欠です。
- そもそも吹き抜け工事に対応可能か。
- 対応可能な場合、追加料金はいくらかかるのか(足場代、高所作業費など)。
- 天井補強や新規配線が必要になった場合、対応できるのか。
結論として、天井高が低く、下地や配線がすでに整っているような簡単なケースであれば、家電量販店への依頼も有効な選択肢です。
しかし、少しでも複雑な工事が予想される吹き抜けへの設置の場合は、より慎重な業者選びが求められます。
最初からシーリングファン専門店やリフォーム会社など、高所作業の実績が豊富な専門業者に相談し、比較検討することをおすすめします。

戸建てやマンションでの注意点
シーリングファンを設置する際の注意点は、建物の構造や規約が異なる戸建てとマンションで、それぞれ押さえておくべきポイントがあります。
ご自身の住居タイプに合わせた確認を怠ると、後々大きなトラブルに発展する可能性もあるため注意が必要です。
戸建ての場合:最重要課題は「天井の強度」
戸建て、特に在来工法などの木造住宅の場合、最も注意すべき点は、繰り返しになりますが「天井の強度」です。
新築時に設置を計画していれば、ハウスメーカーや工務店が設計段階でファンを設置する位置に予め下地補強を行ってくれます。
しかし、後付けの場合は、天井裏の梁や根太といった構造材の位置を正確に探し出し、そこにしっかりと固定する必要があります。
見た目では分からない天井裏の構造を無視し、強度のない石膏ボード部分に取り付けてしまうと、ファンの重みと運転時の継続的な振動で天井が徐々に破損します。
最悪の場合、それが運転中にファンが落下するという重大な事故につながる危険性があります。
後付けを検討する場合は、絶対に自己判断せず、リフォーム会社や専門業者に依頼し、必ず天井裏の構造を点検してもらった上で、最適な補強方法を含めた工事計画を立ててもらいましょう。
点検口がない場合は、天井に点検口を新設する工事(費用2~3万円程度)から必要になることもあります。
マンションの場合:確認すべきは「管理規約」と「天井の構造」
マンションでシーリングファンを設置する場合、戸建てとは異なる2つの大きなハードルがあります。
第一に、「管理規約の確認」です。
マンションではコンクリート躯体(スラブ)は共用部分ですが、内装の仕上げ(クロスなど)は専有部分とされます。
ただし、アンカー打設や穴あけは規約で制限されることが多いため、必ず管理組合に事前確認が必要です。
工事を計画する前に、必ず管理組合に工事内容を説明し、許可を得る必要があります。これを怠ると、後から規約違反を指摘され、原状回復を求められるといった深刻なトラブルになりかねません。
なお、賃貸マンションの場合は、退去時の原状回復義務があるため、原則として穴あけを伴う設置は不可能です。
第二に、「天井の構造の確認」です。
マンションの天井は、コンクリートスラブに直接クロスが貼られている「直天井」と、コンクリートスラブとの間に空間を設けて天井ボードが張られている「二重天井」の2種類があります。
直天井の場合、重量物を吊るすことが構造上想定されておらず、設置は非常に困難で費用も高額になります。
多くの場合は二重天井ですが、天井裏の懐(ふところ)と呼ばれる空間が狭く、十分な補強工事が難しいケースもあるため、こちらも専門家による事前の現地調査が不可欠です。

依頼前に!吹き抜けシーリングファンの工事費用と注意点
- 後付け配線が必要になるケース
- ヘーベルハウス・パナソニック・リクシルへの依頼
- 自分でDIYする場合のリスクと法的注意点
- 掃除のための昇降機後付けという選択肢
- 補助金や保険は適用されるのか
- 吹き抜けシーリングファン工事費用の総まとめ
後付け配線が必要になるケース
新築時にシーリングファン用の設備を計画せず、後から「やっぱりあの吹き抜けにファンを付けたい」と思い立った場合、「電源をどう確保するか」という問題が大きな課題となります。
ファンを取り付けたい吹き抜けの天井に、既存の照明器具などがなく、電源が全く来ていないケースでは、新たに壁や天井の内部に電線を通す「新規配線工事」が必須となります。
この工事は、ただ電線を持ってくるだけではありません。
壁のスイッチからファンを操作できるようにするため、スイッチボックスから天井まで配線を通したり、場合によっては分電盤から専用の回路を設けたりする必要があり専門的な技術と知識を要します。
主な配線ルートとしては、以下の方法が考えられます。
- 最寄りのスイッチやコンセントから分岐させる方法
- 比較的短い距離で配線できますが、元の回路の容量に余裕があるか確認が必要です。
- 分電盤から専用回路を引く方法
- 最も安全で確実ですが、距離が長くなるため工事費は高額になります。
配線工事に伴う高額な追加費用と内装工事のリスク
新規配線工事の費用は、配線ルートの距離や建物の構造(木造、鉄骨など)による難易度によって大きく変動し、20,000円~50,000円以上かかることもあります。
そして、それ以上に考慮すべきなのが、内装への影響です。
壁や天井の内部に電線を通す(隠蔽配線)ためには、ルート上の壁紙(クロス)や天井の石膏ボードを一度部分的に剥がしたり、穴を開けたりする必要があり、工事後にその補修作業が発生します。
そのため、純粋な電気工事費に加えて、内装工事費(クロス張替えなど)も別途発生することを念頭に置かなければなりません。
補修箇所が広範囲に及ぶと、内装工事費だけで数万円以上かかることもあります。
このように、後付けで配線から行う場合は、ファン本体や設置費用だけでなく、電気工事と内装工事の費用も合わせた総額で予算を考える必要があります。
見た目を気にしないのであれば、配線を壁や天井の表面に這わせて樹脂製のモールで隠す「露出配線」という安価な方法もあります。
ただこの方法はデザイン性を損なうため、おしゃれな吹き抜け空間ではあまりおすすめできません。

ヘーベルハウス・パナソニック・リクシルへの依頼
シーリングファンの設置は、家を建ててくれたハウスメーカー(例えばヘーベルハウスのような大手)や、住宅設備を幅広く扱うメーカー(パナソニックやリクシルなど)に依頼する方法があります。
これらの業者に依頼することも、もちろん有力な選択肢の一つです。
ハウスメーカーに依頼する最大のメリットは、何と言っても自宅の構造を隅々まで熟知していることによる絶大な安心感です。
設計図や仕様書が保管されているため、天井裏の梁の位置や太さ、配線ルートなどを正確に把握しており、最も安全で効率的な補強方法や設置場所を的確に提案してくれます。
工事後の保証など、アフターサービスが手厚い点も大きな魅力と言えるでしょう。
一方で、パナソニックやリクシルといった大手メーカーは、自社ブランドのシーリングファン(照明一体型など)を多数ラインナップしています。
そして、リフォーム部門を通じて製品の販売から工事までを一貫して請け負う場合があります。
製品に関する専門知識が非常に豊富で、住まい全体のデザインや機能性を考慮したトータルコーディネートを提案してくれることが期待できます。
ただし、これらの大手メーカーに依頼する場合、一般的に費用は専門の工事業者やリフォーム会社に直接依頼するよりも割高になる傾向があります。
その理由は、多くの場合メーカーが直接工事を行うのではなく、提携する下請けの工務店や業者に再発注する形になるため、その間に発生する中間マージンが価格に上乗せされるからです。
また、対応エリアや工事内容によっては、そもそも対応できないケースもあります。
まとめると、「高くてもいいから、とにかく安心して任せたい」という場合はハウスメーカーへ、「製品選びからこだわってトータルで提案してほしい」場合はパナソニックやリクシルを選択しましょう。
そして「コストを抑えつつ専門的な工事を依頼したい」場合は、実績豊富なシーリングファン専門店やリフォーム会社へ、というように、ご自身が何を最も重視するかで依頼先を検討するのがおすすめです。

自分でDIYする場合のリスクと法的注意点
インターネットやホームセンターで様々な情報が手に入る現代、「少しでも費用を抑えたい」と考え、シーリングファンの設置を自分でDIYしようと検討する方もいるかもしれません。
しかし、結論から言えば、特に吹き抜けへの設置は、専門家でない方が行うにはあまりにもリスクが高すぎるため、絶対に避けるべきです。
DIYには、主に以下の3つの、取り返しのつかない事態に繋がりかねない重大なリスクが伴います。
1. 身体へのリスク(落下・転落事故)
吹き抜けでの作業は、数メートルの高さにある不安定な足場の上で、10kg以上にもなる重いファン本体を頭上に持ち上げながら、細かい配線作業やネジ止めを行うという、非常に危険な作業です。
プロの職人でさえ細心の注意を払うこの作業で、慣れない方がバランスを崩して自分が転落すれば大怪我につながります。
また、工具や部品、最悪の場合はファン本体を落としてしまい、床や大切な家具を傷つけるだけでなく、下にいる家族が巻き込まれるという大惨事につながる可能性があります。
2. 家屋へのリスク(設置不良による故障・落下)
シーリングファンを安全に支えるには、天井裏のどの構造材に、どのくらいの太さのネジで、どのように固定すべきかという専門的な判断が不可欠です。
この判断を誤り、強度のない石膏ボード部分にアンカーだけで固定したり、ネジの締め付けが甘かったりすると、運転時の振動でファンが徐々に緩み、異音や故障につながります。
最悪の場合、それが運転中に天井から落下するという、命に関わる重大な事故を引き起こす恐れがあります。
3. 法的なリスク(無資格工事による違法性と保険の問題)
そして最も重要な点として、既存の引掛シーリングなどを介さず電源コードを直接器具に接続したり、新たに壁の中から配線を行ったりする工事には法律上の決まりがあります。
これらの工事は、電気工事士の資格が必要」と法律で定められています。無資格での施工は違法であり、事故時に保険も適用されません。
万が一、その無資格工事が原因で漏電や火災が発生した場合、刑事罰の対象になる可能性があるだけでなく、火災保険が一切適用されないという、経済的にも壊滅的な事態を招く可能性があります。
結論として、吹き抜けへのシーリングファン設置は、節約できる費用とは比較にならないほどのリスクを伴うため、DIYで行うべきではありません。
ご自身とご家族の安全、そして大切な住まいを守るため、必ず適切な資格を持った専門業者に依頼してください。
横浜・川崎・東京都南部エリアで業者をお探しの方へ
もし、設置に関するご不安な点や、「うちの吹き抜けでも大丈夫かな?」といったご相談がありましたら、いつでもお気軽に私たち「横浜電気工事レスキュー」へお問い合わせください。
シーリングファン設置に伴う天井の補強やクロスの張り替えなど、住宅リフォームのご相談も専門部門が合わせて承ります。
経験豊富なスタッフが、お客様の状況に合わせて親身にアドバイスさせていただきます。

掃除のための昇降機後付けという選択肢
シーリングファンを設置した多くの方が、後になって直面する最大の悩み、それが「掃除」の問題です。
吹き抜けの高い位置で回転するファンには、想像以上にホコリが溜まります。特に羽根の上面は、数ヶ月もすれば黒いホコリの層ができてしまいます。
その都度、足場を組んで専門業者に掃除を依頼すれば数万円の費用がかかりますし、自分で長い柄のモップを使って掃除するのも、体勢が不安定で危険が伴います。
その深刻な悩みを根本から解決する画期的なアイテムが「電動昇降機(しょうこうき)」です。
これは、壁のスイッチ操作だけでシーリングファンをワイヤーで安全に手の届く高さまで自動で降ろせる、非常に便利な装置です。
掃除や、照明付きモデルの場合は電球交換などが終わったら、再び元の天井位置へ戻すこともできます。
昇降機は後付けも可能!長期的な視点で検討を
この電動昇降機は、シーリングファンを新しく設置する時だけでなく、既に設置されているファンを取り外し、昇降機を取り付けてから再度ファンを設置する、という形で後付けすることも可能です。
昇降機の本体価格は10万円前後から、そして取り付け工事費もかかりますので、初期投資は決して安くはありません。
しかし、清掃業者に依頼すると1回数万円かかりますし、自分で掃除するにはリスクと大変な労力が伴います。
この点を考えれば、特にご高齢の方や高所での作業に不安があるご家庭にとって、これは安全で快適なシーリングファンライフを末永く送るための、非常に価値ある投資と言えるでしょう。
シーリングファンの設置を計画する段階で、この昇降機の存在を知っているかどうかで、将来のメンテナンス性が大きく変わってきます。ぜひ選択肢の一つとして検討してみてください。

補助金や保険は適用されるのか
高額になりがちな吹き抜けへのシーリングファン設置費用。「国や自治体の補助金や、加入している火災保険などを使って、少しでも負担を減らせないだろうか」と考える方もいるかもしれません。
ここでは、その可能性について解説します。
補助金について:直接的な制度はほぼ皆無
結論から言うと、2025年現在、シーリングファン設置そのものを直接の対象とした、国やほとんどの自治体の補助金・助成金制度は、残念ながら存在しません。
シーリングファンは省エネ効果が期待できる設備ではありますが、エアコンや給湯器、窓の断熱改修といった、よりエネルギー消費の大きい設備が補助金の主な対象となっているのが現状です。
ただし、国や自治体が行う大規模な省エネリフォーム補助金において、断熱改修や高効率空調設備の導入といった必須工事と併せて行う場合、補助対象となる可能性があります。
リフォーム全体で検討する際は、施工業者に対象となるか確認してみることをお勧めします。
補助金制度は年度や自治体によって目まぐるしく内容が変わるため、最新の正確な情報をリフォーム業者や自治体のホームページで確認することが重要です。
火災保険について:適用は災害による損害時のみ
火災保険は、その名の通り、火災や、契約内容によっては自然災害(台風、落雷、雹災など)によって建物や家財に損害を受けた場合に、その修理費用を補償するものです。
そのため、通常のリフォームや、経年劣化による故障、新規設置工事の費用を補填するために利用することはできません。
ただし、例外として、以下のようなケースでは保険が適用される可能性があります。
- 台風による強風で屋根や窓が破損し、その結果吹き込んだ雨水によってシーリングファンが故障した。
- 近所に落雷があり、その影響による過電流(誘導雷サージ)でモーターが故障した。
このような場合は、事故として保険会社に申請できる可能性があります。
また、前述の通り、無資格業者によるずさんな電気工事が原因で火災が発生した場合などは、重大な契約違反とみなされ保険金が支払われないリスクがあるため、業者選びは慎重に行いましょう。

吹き抜けシーリングファンの工事費用:総まとめ
この記事では、吹き抜けへのシーリングファン設置に関する費用から業者選び、法的な注意点、そして長期的なメンテナンスに至るまで、あらゆる角度から網羅的に解説しました。
最後に、後悔しないシーリングファン設置を実現するための重要なポイントをリスト形式で最終確認しましょう。
- 吹き抜けの工事費用は天井高に比例して高額になる
- 費用内訳は「基本工賃」「高所作業費」「足場代」の合計で考える
- 天井の強度が不足している場合は10万円以上の補強工事が追加で必要になる
- 単なる照明交換とは異なり、専門技術を要する建築・電気工事である
- 最大のメリットは空気循環による冷暖房効率の向上と電気代の節約
- 最新の高気密高断熱住宅では費用対効果が低い場合もある
- デメリットは高額な初期費用と、高所の掃除・メンテナンスの負担
- 業者選びは吹き抜けでの豊富な設置実績を最優先事項とする
- 最低3社から詳細な項目が記載された相見積もりを取ることが失敗を防ぐ鍵
- 配線工事には「電気工事士」の国家資格が法律で定められている
- 家電量販店は手軽だが、高所や補強といった特殊工事の対応力は要確認
- ハウスメーカーは構造を熟知しており安心感は高いが、費用は割高になる傾向
- 転落や落下の危険、法的な問題からDIYでの設置は絶対に避けるべき
- 掃除の負担を劇的に軽減する電動昇降機は後付けも可能な価値ある選択肢
- シーリングファン設置単体を対象とした補助金は現状ほとんど存在しない