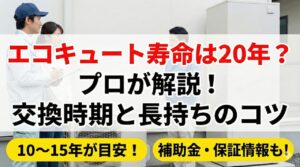床暖房の後付けで後悔しない!費用とデメリットをプロが解説

こんにちは。横浜電気工事レスキューの主任電気工事士「天谷富士夫」です。
冬の寒さが厳しくなり、フローリングの冷たさが身に染みる季節になると、足元からじんわりと暖まる床暖房のリフォームを検討される方が増えてきます。
しかし、いざ導入しようとネットで調べ始めると「光熱費が高すぎて結局使わなくなった」「工事費が思ったより高額で元が取れない」「床に段差ができてつまづくようになった」といった後悔の声を目にして、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
特にマンションにお住まいの方や、電気式とガス温水式のどちらが良いか迷っている方にとって、決して安くない投資だけに失敗は避けたいものです。
この記事では、現場で数多くの設備トラブル対応や交換工事を行ってきた私の視点から、床暖房の後付けリフォームに関するリアルな費用相場やメリット・デメリット、そして後悔しないための選び方を分かりやすく解説します。
記事のポイント
- 床暖房を後付けする際の具体的な工事費用と工法別の相場
- 電気式と温水式のランニングコストやメンテナンス性の違い
- マンションや中古住宅でリフォームする際の管理規約と注意点
- 「暖まらない」「ゴキブリが出る」といった悪い口コミの真偽と対策
- 1. 床暖房を後付けして後悔しないための費用と相場
- 1.1. 後付けリフォームの費用相場と比較表をチェック
- 1.2. マンションへの床暖房後付け費用と管理規約
- 1.2.1. ここが重要
- 1.3. 中古住宅のリフォームで床暖房を入れる値段
- 1.4. フローリング張替えと上張りの費用と工法の違い
- 1.4.1. 上張り工法(重ね張り)
- 1.4.2. 張替え工法
- 1.5. 東京ガスの温水式床暖房リフォーム費用を解説
- 1.6. ガスと電気はどっちが安い?ランニングコスト比較
- 1.6.1. 電気式(PTCヒーターなど)
- 1.6.2. ガス温水式
- 1.7. 設置で固定資産税はいくら上がる?
- 1.8. 自分で出来る?床暖房の後付けDIYとキット
- 2. 床暖房の後付けで後悔する理由と対策を徹底解説
- 2.1. ブログや知恵袋・2chで見られる後悔の理由
- 2.2. 口コミで分かるメリットとデメリットの真実
- 2.2.1. メリット
- 2.2.2. デメリット
- 2.3. 電気式床暖房のメリットとデメリットを深掘り
- 2.4. 暖まるのが遅い?エアコンとどっちが暖かいか
- 2.5. エアコンと床暖房の電気代や光熱費を徹底比較
- 2.6. 床の段差やメンテナンスの手間で後悔するケース
- 2.7. 床暖房はゴキブリを発生させる?噂の真相
- 2.8. そもそも床暖房はいらない?後付けして後悔しないための結論
床暖房を後付けして後悔しないための費用と相場
床暖房を後付けする場合、最もハードルとなるのが「工事にいくらかかるのか」という初期費用の問題です。
チラシなどで見る「床暖房リフォーム◯◯万円〜」という価格は最低限の仕様であることが多く、実際に見積もりを取ると倍以上の金額になることも珍しくありません。
ここでは、後から予算オーバーで後悔しないために知っておくべき費用の相場と、それぞれの工法の違いについて、現場の感覚を交えて詳しく見ていきましょう。
後付けリフォームの費用相場と比較表をチェック
床暖房のリフォーム費用は、大きく分けて熱源の種類(電気式か温水式か)と、施工方法(上張りか張替えか)の組み合わせで決まります。
それぞれの特徴と、6畳〜8畳程度の広さを想定した場合の費用相場を比較表にまとめました。
| 種類・工法 | 費用相場(6畳目安) | 特徴と注意点 |
|---|---|---|
| 電気式(上張り) | 約35万〜55万円 | 既存床の上に貼るため最も安価。工期も1〜2日と短いが、床が高くなる。 |
| 電気式(張替え) | 約55万〜80万円 | 床を剥がすため解体費がかかる。段差はなく仕上がりが綺麗。 |
| 温水式(上張り) | 約60万〜90万円 | 熱源機(給湯器)の交換が必要になるケースが多い。配管工事が必要。 |
| 温水式(張替え) | 約80万〜120万円超 | 解体、大工工事、配管、熱源機交換を含み最も高額。大規模リフォーム向け。 |
電気式の上張り工法が一番リーズナブルですが、それでも数十万円の出費にはなります。逆に、温水式で床を全て張り替えるとなると、100万円以上かかることも珍しくありませんね。
電気式の場合は、これに加えて「専用回路の増設工事」が必要になることがほとんどです。
分電盤に空きがない場合は盤自体の交換も必要になるため、プラス5万〜10万円程度の電気工事費を見込んでおくのが無難です。

マンションへの床暖房後付け費用と管理規約
マンションでの床暖房後付けは、戸建てよりも難易度が高く、費用も割高になる傾向があります。その最大の理由は「管理規約」と「遮音性能」の壁です。
多くのマンションでは、階下への騒音トラブルを防ぐため、床材の遮音等級を「L-45」や「L-40」以上に規定しています。
リフォームで床暖房を入れる際も、この基準を満たす「防音クッション付きの床暖房対応フローリング」を使用しなければなりません。この特殊な床材は、一般的なフローリングよりも材料費が高くなります。
ここが重要
温水式を導入したい場合、パイプスペース(PS)内の給湯器を「暖房機能付き」に交換する必要があります。
しかし、マンションの構造によっては配管を通す穴(スリーブ)が新たに開けられなかったり、規約でガス給湯器の号数アップ(例:16号→24号)が禁止されていたりすることもあります。
工事を依頼する前に、必ず管理組合の規約を確認し、理事会への工事申請手続きを行うことがトラブル回避の第一歩です。
許可が降りるまでに1ヶ月以上かかることもあるので、スケジュールには余裕を持ちましょう。

中古住宅のリフォームで床暖房を入れる値段
中古住宅を購入してリノベーションするタイミングで、床暖房を入れたいという相談もよくいただきます。
この場合、単に床暖房のパネルを入れるだけでなく、「床下の断熱処理」をセットで考えることが非常に重要です。
築20年以上の古い住宅の場合、床下の断熱材が入っていない、あるいは薄くて劣化していることがよくあります。
そのまま床暖房を入れても、せっかくの熱が床下に逃げてしまい「ガス代・電気代が高いのに全然暖まらない」という最悪の後悔につながりかねません。
床を剥がして施工する「張替え工法」を選ぶなら、必ず床下の状態を確認し、高性能な断熱材の充填も含めた見積もりを取るようにしましょう。
費用はプラス数万円〜十数万円かかりますが、ランニングコストの削減効果で十分元が取れるはずです。
フローリング張替えと上張りの費用と工法の違い
費用を抑えるなら「上張り(重ね張り)」、仕上がりとバリアフリーを重視するなら「張替え」というのが基本的な選び方です。
上張り工法(重ね張り)
今の床の上に温水マットや電熱パネルを敷き、その上から新しいフローリングを貼ります。
解体工事がないので廃材も出ず、工期も短く済みます。ただし、床全体が12mm〜15mm程度高くなるというデメリットがあります。
上張りの注意点
床が上がると、ドアが開かなくなったり、クローゼットの扉と干渉したりします。
これを防ぐためにドアの下部をカットする工事や、廊下との段差を解消するスロープ(見切り材)の設置が必要となり、その分の追加費用が発生します。
張替え工法
既存の床を撤去して根太(ねだ)や下地が見える状態にし、そこに床暖房パネルを設置してから新しい床材を貼ります。
床の高さが変わらないため、バリアフリーを維持でき、段差につまずくリスクもありません。ただし、解体処分費と大工手間がかかる分、費用は高くなりますし、工事中の騒音やホコリも多くなります。

東京ガスの温水式床暖房リフォーム費用を解説
関東エリアにお住まいの方なら、東京ガスの「TES(テス)」と呼ばれる温水システムをご存知の方も多いでしょう。
東京ガスグループや認定店でリフォームを依頼する場合、機器の選定から施工まで一貫して任せられる信頼性は抜群ですが、費用は一般的なリフォーム店よりやや高めになる傾向があります。
具体的には、6畳〜10畳程度のリビングで熱源機(給湯器)の交換も含めると、総額で60万〜90万円程度を見込んでおいた方が良いでしょう。
特に、既存の給湯器がまだ新しく使える状態なのに、「暖房機能がない」という理由だけで高額な暖房付き給湯器に交換しなければならない場合、かなりもったいないと感じるかもしれません。
ただ、東京ガスには床暖房利用者向けの「暖らんぷらん」などのガス料金割引メニューがあるので、ランニングコストを含めた10年単位のトータルバランスで考えるのが正解かなと思います。
(参考:ガス温水床暖房の活用方法|東京ガス )

ガスと電気はどっちが安い?ランニングコスト比較
「工事費は電気が安くて、毎月の光熱費はガスが安い」とよく言われますが、これは半分正解で半分は条件次第です。
なお、ここで言う「電気式」とは、リフォームで手軽に導入できる「電熱線ヒーター式(PTCヒーター等)」を指します。
実際に私がお客様に目安としてお伝えしているのは、8畳のお部屋で1日8時間使った場合のイメージです。
断熱性能やプランにもよりますが、都市ガスの温水式は月3,500〜6,000円前後、電気ヒーター式は月7,000〜12,000円前後になることが多いです。
電気式(PTCヒーターなど)
立ち上がりが比較的早いのがメリットですが、電気料金単価の影響をモロに受けます。 長時間・広範囲で使うと電気代が跳ね上がり、「怖くて使えない」となりがちです。
そのため、朝晩の短時間利用や、キッチン・脱衣所などの「狭い範囲をピンポイントで温めたい場所」に向いています。
ガス温水式
立ち上がりにエネルギーを使いますが、一度温まると少ないガス量で保温しやすく、長時間(1日8時間以上など)じっくり使うなら電気式より割安になるケースが多いです。
初期費用はかかりますが、「家族が集まるリビングをメイン暖房として長時間使う」なら、ランニングコストで元が取れるこちらがおすすめです。
ここが電気屋としての重要ポイント
電気式を導入する場合、ご家庭の契約アンペア数には本当に注意してください。
床暖房はそれだけで数十アンペア消費することもあり、既存の30A・40A契約のままだと、ドライヤーを使った瞬間にブレーカーが落ちるなんてことが頻発します。
『電気工事の基礎知識:分電盤の交換費用と注意点を徹底解説』の記事でアンペア数や分電盤について詳しく解説していますので、古い設備の方は合わせてチェックしてみてください。

設置で固定資産税はいくら上がる?
意外と見落としがちなのが税金の話です。新築時であれば、床暖房は「家屋の価値を高める設備」として固定資産税の加点対象になります。
しかし、「リフォーム(後付け)」の場合は、少し事情が異なります。
意外と知られていませんが、内装の張り替えや設備の交換といった「建築確認申請を伴わない規模」の後付けリフォームであれば、実務上は自治体による家屋調査がすぐに行われることは少ないです。
そのため、その年から固定資産税が大きく増えるケースは多くありません。
ただ、床暖房のような設備のグレードアップは、本来であれば家屋の価値が上がるため、評価見直しの対象になり得ます。
とはいえ、そこまで身構える必要はありません。 リビングなどに後付けする程度であれば、税額への影響は年間で数百円〜数千円(ランチ1回分程度)の増額に収まるケースがほとんどだからです。
リフォームの内容や金額によっては、将来的な評価替えのタイミングなどで固定資産税が増額される可能性もありますので、最終的にはお住まいの自治体(資産税課など)に電話で確認しておくと安心ですよ。
(参考:総務省|地方税制度|固定資産税)

自分で出来る?床暖房の後付けDIYとキット
最近はネット通販で「DIY用床暖房キット」のような商品も見かけます。
「自分でやれば工事費が浮くかも」と思う気持ちは痛いほど分かりますが、プロの電気工事士としては「絶対にやめてください」と強く反対します。
まず、壁や床の中に配線を固定する工事は、法律(電気工事士法)で定められた「電気工事」にあたるため、無資格での施工は違法です。
メーカーの施工マニュアルを見ても、必ず「施工は有資格者が行うこと」と明記されています。
もし無資格の方が施工して、接続不良で火災や漏電事故が起きた場合どうなるか。
命の危険があるのはもちろんですが、「正しい施工をしていない」とみなされ、メーカー保証も一切受けられませんし、火災保険すら降りない可能性が高いのです。
これでは、節約どころか人生を棒に振るリスクがあります。
また、温水式をDIYで行うのも、水漏れのリスクが高すぎて論外です。
施工不良で階下への水漏れを起こしてしまった場合、賠償額は莫大になりますが、ここでも「素人工事」が原因だと保険のトラブルになりかねません。
「安全と安心をお金で買う」。 床暖房に関しては、必ず電気工事士や管工事の資格を持った専門業者にお任せいただくのが、結果的に一番安くつく選択ですよ。
床暖房の後付けで後悔する理由と対策を徹底解説
ここからは、実際に床暖房を導入した方が「失敗した」「やらなきゃよかった」と感じてしまった具体的な理由と、そうならないための対策を深掘りしていきます。
ネット上の口コミや現場のお客様から聞いた生の声をもとにしていますので、ぜひ参考にしてください。
ブログや知恵袋・2chで見られる後悔の理由
ネットの掲示板やブログ、知恵袋などをリサーチしてみると、後悔の理由は大きく以下の3つに集約されます。
- 光熱費が想像以上に高かった
「最初の請求書を見て驚愕し、それ以来怖くてスイッチを入れなくなった」というケース。特に断熱性の低い家で電気式を入れた場合に多いです。 - 暖まるまでに時間がかかりすぎる
「寒い朝、すぐに暖まりたいのに1時間経ってもなんとなく暖かい程度」という不満。エアコンのような即暖性を期待してしまったパターンです。 - メンテナンス費用がかさむ
「給湯器が壊れて修理費が高額」「10年経って不凍液の交換が必要と言われた」など、ランニングコスト以外の維持費に驚く声です。
これらは、「床暖房の特性」を事前に理解し、正しい対策を講じていれば防げたギャップかもしれません。
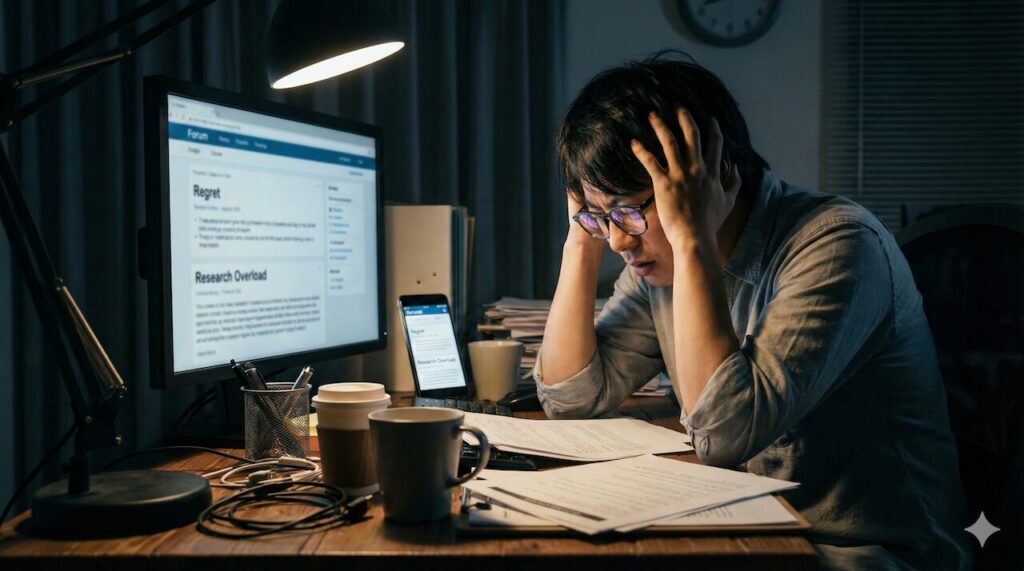
口コミで分かるメリットとデメリットの真実
もちろん悪い話ばかりではありません。「一度使ったらやめられない」「エアコンの風がなくて快適」という絶賛の口コミも多いです。メリットとデメリットは表裏一体なんですね。
メリット
・足元からポカポカする「頭寒足熱」の心地よさ。
・エアコンのように風が出ないので、ホコリやハウスダストが舞わない。
・温風による過度な乾燥を防げる。
・暖房器具が部屋に出ないので、インテリアがすっきりする。
デメリット
・初期費用が高額。
・スイッチを入れてから暖まるまで30分〜1時間かかる(即暖性がない)。
・部屋全体が暖まるには時間がかかる。
・故障時の修理が床を剥がすなど大掛かりになりやすい。
このデメリットを許容できるか、あるいは他の暖房器具と併用してカバーできるかが、満足度の分かれ道になります。
電気式床暖房のメリットとデメリットを深掘り
電気式は初期費用が比較的安く、給湯器の交換も不要なのでリフォームでは人気があります。しかし、導入にあたってはいくつか注意点があります。
まず、「電気容量(アンペア数)」の問題です。床暖房はかなりの電力を消費します。例えば10畳用で2000W近く消費することもあり、これだけで20アンペア分を使ってしまいます。
古いマンションで契約アンペア数が30Aや40Aの場合、床暖房を入れた状態でドライヤーや電子レンジを使うと、すぐにブレーカーが落ちてしまいます。
これを防ぐには、契約アンペアを上げる必要がありますが、建物全体の電気容量制限で上げられないケースもあります。
また、電熱線の上に座布団やクッションを置きっぱなしにすると熱がこもって床が変色したり、ヒーターが傷んだりする「熱ごもり」にも注意が必要です。
最近は温度を自動制御する「PTCヒーター」など、こうしたデメリットを解消した製品も出ているので、製品選びは慎重に行いましょう。
暖まるのが遅い?エアコンとどっちが暖かいか
「暖かさ」の質で言えば、輻射熱(遠赤外線)で体の芯から温める床暖房の圧勝です。エアコンは空気を温めるだけなので、どうしても「顔は熱いのに足元は寒い」という状態になりがちです。
しかし、「速さ」ではエアコンに軍配が上がります。「寒い!」と思ってスイッチを入れても、床暖房(特に温水式)が本領を発揮するには30分〜1時間かかります。
このタイムラグにイライラして後悔する方が多いのです。対策としては、「起床の1時間前にタイマー予約をする」か、「立ち上がりの30分間だけエアコンを併用して部屋を温める」のが賢い使い方です。

エアコンと床暖房の電気代や光熱費を徹底比較
正直に言っちゃいますが、「光熱費の安さ」だけで選ぶなら、最新のエアコンが最強です。
最新のエアコンは「ヒートポンプ」という技術の効率がものすごく良く、少ない電力で大きな熱エネルギーを生み出せるからです。
「同じ室温にする」という条件で単純なコスト比べをしたら、残念ながら床暖房はエアコンには勝てません。
床暖房は、先ほど試算したように月々3,500円〜10,000円前後の光熱費がプラスになるとお考えください。 ですので、これは「節約のための設備」ではありません。
「この数千円で、あの不快なエアコンの風や乾燥、足元の冷えから解放される『快適さ』を買う」 そう割り切れるかどうかが、後悔しないための最大の判断ポイントになります。
「多少コストがかかっても、冬場のQOL(生活の質)を上げたい」 そう感じる方にとっては、その金額以上の価値が間違いなくある設備です。
『床暖房とエアコンではどちらが安い?光熱費とコストを比較』記事でさらに詳しく比較しています。
床の段差やメンテナンスの手間で後悔するケース
上張り工法で設置した結果、「廊下との1cmちょっとの段差に毎日つまずくようになった」という高齢の方からの相談もあります。
若い方には気にならない段差でも、年齢を重ねると大きな障害になります。また、お掃除ロボット(ルンバなど)が段差を乗り越えられず、掃除エリアが制限されてしまったという声も聞きます。
また、温水式の場合、10年〜15年程度で熱源機の交換時期が来ますし、メーカーによっては数年に一度の不凍液の補充や交換(数万円)が必要です。
設置して終わりではなく、将来的なメンテナンスコストも発生することを覚えておきましょう。
ここを計算に入れていないと、将来「維持費が高いから修理せずに放置してただの床になった」という悲しい結果になってしまいます。

床暖房はゴキブリを発生させる?噂の真相
「床暖房を入れるとゴキブリが出る」という都市伝説のような噂を聞いたことはありませんか? 結論から言うと、床暖房の機械自体がゴキブリを発生させるわけではありません。
ただ、ゴキブリは25℃〜30℃程度の暖かくて暗い場所を好みます。冬場でも床下が暖かく、かつ適度な湿気がある環境になれば、彼らにとって居心地が良い場所になってしまう可能性は否定できません。
しかし、これは床暖房のせいというより、「家の隙間」の問題です。しっかりとした気密処理を行い、配管の貫通部などの隙間をパテやコーキングで完全に塞げば、外部からの侵入は防げます。
特に、リフォーム時は壁や床に穴を開けるため、普段より隙間ができやすいタイミングです。業者に「配管周りの隙間埋め(防虫処理)を徹底してほしい」と一言伝えておくだけで、リスクは激減します。
そもそも床暖房はいらない?後付けして後悔しないための結論
最後に、私の個人的な見解も含めた結論をお伝えします。
もし、ご自宅の断熱性能が低く、窓がシングルガラスで冬場に冷気が降りてくるような状態であれば、床暖房よりも先に「内窓(二重窓)」の設置や「断熱リフォーム」を優先すべきです。
断熱性の低い家で床暖房を使っても、熱が外に逃げるばかりで光熱費が無駄にかかり、部屋も暖まりません。
逆に、ある程度の断熱性があり、「家族が集まるリビングだけは快適にしたい」「足元の冷えを根本的に解消したい」という明確な目的があるなら、床暖房は生活の質を劇的に向上させる最高の設備になります。
後悔しないためには、「即暖性はないこと」「ランニングコストはかかること」「段差やメンテナンスのリスク」を理解した上で、信頼できる業者にしっかりとした施工(特に断熱処理と隙間埋め)を依頼すること。
これが全てかなと思います。