電気温水器の電気代が高すぎる!原因と節約術をプロが解説
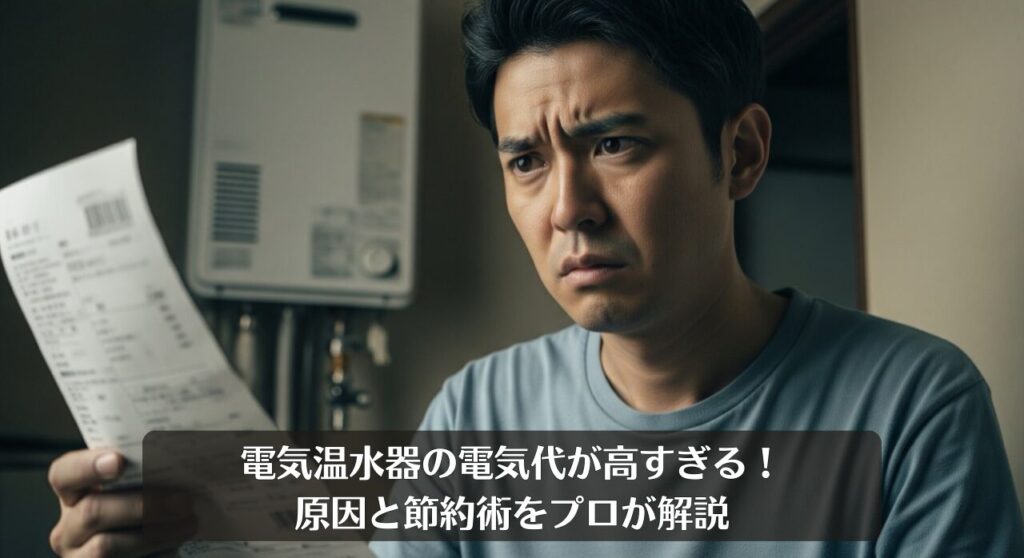
冬になると請求額が跳ね上がる電気温水器の電気代、なぜこんなに高すぎるのかと悩んでいませんか。特に古いマンションにお住まいの場合、設備の漏電や性能低下が原因かもしれません。
また、夜間電力プランの変更や契約アンペア、100Vと200Vの違いも電気代に影響します。
一人暮らしや賃貸では対策が限られると感じる一方、電源をつけっぱなしにするのが良いのか、こまめに消すべきなのか、知恵袋で節約方法を探す方も多いでしょう。
現在の光熱費が平均と比べてどうなのか、ガス給湯器やエコキュートへの交換費用はいくらかかるのか、この記事では、そうした疑問に専門的な視点からお答えします。
記事のポイント
- 電気温水器の電気代が高くなる根本的な理由
- 今日から実践できる具体的な電気代節約術
- 賃貸やマンションなど住居形態別の注意点
- エコキュートへの交換費用と国の補助金制度
- 1. 電気温水器の電気代が高すぎる5つの原因
- 1.1. なぜこんなに高いのか?
- 1.2. 冬になると特に電気代が上がる理由
- 1.3. 平均額と自宅の料金を比較
- 1.4. 電源つけっぱなしは本当に損なのか?
- 1.5. 古いマンションに潜む漏電のリスク
- 1.5.1. 効率の低下
- 1.5.2. 漏電の可能性
- 1.6. 夜間電力プラン変更が与える影響
- 2. 電気温水器の電気代が高すぎる問題の解決策
- 2.1. 知恵袋に学ぶ今日からできる節約方法
- 2.2. 契約アンペアと100V・200Vの違いとは
- 2.3. 一人暮らしや賃貸物件での対策
- 2.4. 古いマンションで注意すべき漏電の兆候
- 2.5. ガス給湯器やエコキュートへの交換費用
- 2.5.1. 交換にかかる費用の比較
- 2.5.2. 国の補助金制度の活用
- 2.6. 横浜市の近隣エリアで交換ならお任せ!実際の施工事例をご紹介
- 2.7. 電気温水器の電気代が高すぎる悩みの最終手段
電気温水器の電気代が高すぎる5つの原因
- なぜこんなに高いのか?
- 冬になると特に電気代が上がる理由
- 平均額と自宅の料金を比較
- 電源つけっぱなしは本当に損なのか?
- 古いマンションに潜む漏電のリスク
- 夜間電力プラン変更が与える影響
なぜこんなに高いのか?
電気温水器の電気代が高額になる根本的な理由は、お湯を沸かすその仕組み自体にあります。
電気温水器は、タンク内にある電気ヒーターに電気を流し、その熱で直接水を温めるという、いわば巨大な電気ポットのような構造です。
この方法では、消費した電気エネルギーを100%熱エネルギーに変えるのが限界であり、それ以上の効率向上は見込めません。
一方で、近年主流となっているエコキュートは、ヒートポンプ技術を利用します。
これはエアコンの暖房と同じ原理で、少ない電気でファンと圧縮機を動かし、空気中にある熱エネルギーを集めて、その熱でお湯を沸かす仕組みです。
このため、消費した電気エネルギーの3倍から4倍もの熱エネルギーを生み出すことが可能になります。
つまり、同じ量のお湯を沸かすために、電気温水器はエコキュートの3倍以上の電力が必要になるのです。このエネルギー効率の圧倒的な差が、毎月の電気代として大きく反映されることになります。
電気温水器を長く使っている場合、この構造的な非効率性が、電気代が高すぎる最大の原因と考えられます。

冬になると特に電気代が上がる理由
冬の間に電気温水器の電気代が著しく上昇するのには、主に二つの物理的な理由が関係しています。
一つ目は、給水温度の低下です。夏場であれば20℃以上ある水道水の温度が、冬場には10℃未満まで下がることがあります。
電気温水器は、この冷たい水を設定した温度(例えば60℃~80℃)まで温めなければなりません。温めるべき温度差が大きくなるほど、より多くの熱エネルギーが必要となり、結果として電力消費量が増大します。
二つ目は、外気温の低下による放熱です。電気温水器は沸かしたお湯を貯湯タンクに保温していますが、タンクの周囲の温度が低いほど、タンクからの自然な熱の放出(放熱ロス)も大きくなります。
システムは、設定温度を維持するためにより頻繁にお湯を温め直す必要が出てくるため、保温しているだけでも夏場より多くの電力を消費してしまうのです。
これらの理由から、冬場はただお湯を使うだけでなく、お湯をタンクに貯めておくだけでも余分な電気代がかかり、請求額が跳ね上がる要因となります。

平均額と自宅の料金を比較
ご自宅の電気温水器の電気代が高いのかどうかを判断するためには、一般的な平均額と比較してみるのが有効です。
電気代は、お住まいのエリアの電力会社、家族の人数、そして生活スタイルによって大きく変動します。
以下の表は、世帯人数や電力エリアごとの電気温水器にかかる月々の電気代の目安をまとめたものです。ご自身の請求額と見比べて、現状を客観的に把握してみましょう。
| 電力エリア | 月額目安(4人世帯・460 L タンク想定) |
|---|---|
| 北海道電力 | 約16,400円 |
| 東北電力 | 約15,700円 |
| 東京電力 | 約13,100円 |
| 中部電力 | 約 8,400円 |
| 関西電力 | 約 7,300円 |
| 九州電力 | 約 7,100円 |
もし、ご自宅の電気代がこの平均額を大幅に上回っている場合、機器の劣化や使い方、契約プランなどに何らかの問題がある可能性が考えられます。
特に、一人暮らしにもかかわらず2人暮らし世帯の平均額に近い、あるいは超えている場合は、一度詳細な原因調査を検討するべきサインかもしれません。

電源つけっぱなしは本当に損なのか?
電気温水器の電源を「つけっぱなし」にするべきか、それとも使わない時間は切るべきか、という点は多くの方が悩む問題です。
これは一概にどちらが正しいとは言えず、生活スタイルや季節によって最適な使い方が異なります。
電源をつけっぱなしにする場合、多くの電気温水器は自動保温機能が働き、タンク内のお湯が冷めると自動で再加熱します。
この自動保温や、お風呂のお湯を一定温度に保つ追い焚き機能は、常に快適な温度でお湯を使えるメリットがある反面、微量ながら待機電力を消費し続けます。
一方、電源をこまめに切る場合、日中などお湯を使わない時間帯の待機電力は節約できます。
しかし、一度冷めてしまった大量の水を再び設定温度まで温め直す際には、非常に大きな電力が必要となります。
特に冬場はタンクのお湯が冷めやすいため、沸かし直しにかかる電気代が、待機電力を節約した分を上回ってしまう可能性があります。
したがって、家族の入浴時間がバラバラで、日中もお湯を頻繁に使う家庭であれば、電源はつけっぱなしの方が結果的に効率的な場合があります。
逆に、家族が少なくお湯を使う時間が集中している家庭や、夏場などお湯が冷めにくい季節には、使わない時間帯に電源を切ることで節約効果が期待できるでしょう。

古いマンションに潜む漏電のリスク
古いマンションに設置されている電気温水器の場合、経年劣化が電気代高騰の隠れた原因となっていることがあります。特に注意したいのが、効率の低下と漏電のリスクです。
効率の低下
電気温水器を10年以上使用していると、ヒーター部分に水道水に含まれるカルシウムなどのミネラル分が固着し、「スケール」と呼ばれる水垢が蓄積します。
このスケールは断熱材のような役割を果たしてしまい、ヒーターの熱が水に伝わりにくくなります。
結果として、設定温度までお湯を沸かすのにより長い時間と多くの電力が必要となり、知らず知らずのうちに電気代を押し上げていきます。
漏電の可能性
さらに深刻なのが漏電です。長年の使用で内部の部品や配線が劣化すると、電気が本来の回路から漏れ出してしまうことがあります。
漏電は、消費電力を無駄に増やすだけでなく、ブレーカーが頻繁に落ちる原因となったり、最悪の場合は火災や感電事故につながる危険性もはらんでいます。
急に電気代が上がった、ブレーカーが落ちやすくなった、本体から異音がするなどの症状が見られる場合は、単なる使い方の問題ではなく、機器の寿命や故障が原因かもしれません。
安全のためにも、設置から10年以上経過している場合は、一度専門の業者に点検を依頼することをおすすめします。

夜間電力プラン変更が与える影響
かつて電気温水器は、電気料金が大幅に割り引かれる深夜の時間帯にお湯を沸かすことで、ランニングコストを抑えるのが基本的な運用方法でした。しかし、この経済的な前提が近年大きく揺らいでいます。
多くの大手電力会社では、従来の深夜電力プラン(夜間電力プラン)の新規受付を停止し、既存のプランについても料金の値上げや割引率の縮小といった見直しを進めています。
この背景には、エコキュートの普及などによる夜間電力の需要増加や、太陽光発電の普及による昼間の電力価格の低下など、電力市場全体の構造変化があります。
このため、以前と同じようにお湯を使っているだけなのに、契約している電気料金プラン自体が変更されたことで、請求額が以前の倍近くになってしまったというケースも少なくありません。
電気代が急に高くなったと感じる場合、機器の故障や使い方だけでなく、電力会社から届く検針票や契約内容のお知らせを確認し、ご自身が契約しているプランの料金単価、特に夜間時間帯の単価がどう変わったのかを把握することが大切です。
もはや「深夜電力だから安い」という考え方が通用しなくなってきているのが現状です。

電気温水器の電気代が高すぎる問題の解決策
- 知恵袋に学ぶ今日からできる節約方法
- 契約アンペアと100V・200Vの違いとは
- 一人暮らしや賃貸物件での対策
- 古いマンションで注意すべき漏電の兆候
- ガス給湯器やエコキュートへの交換費用
- 横浜市の近隣エリアで交換ならお任せ!実際の施工事例をご紹介
- 電気温水器の電気代が高すぎる悩みの最終手段
知恵袋に学ぶ今日からできる節約方法
電気代を少しでも抑えるためには、日々の使い方を工夫することが有効です。専門的な知識がなくても、今日からすぐに実践できる節約方法がいくつかあります。
まず、給湯温度の設定を見直しましょう。食器洗いや洗顔に使うお湯の温度を、必要以上に高く設定していないでしょうか。
リモコンの給湯温度を少し下げるだけでも、無駄なエネルギー消費を減らすことができます。特に夏場は設定温度を低めにしても快適に使えることが多いです。
次に、お風呂の使い方です。フルオートタイプの自動保温機能は便利ですが、家族の入浴間隔が空く場合はオフにしましょう。
お湯が冷める前に全員が続けて入浴するのが最も効果的な節約です。また、浴槽にお湯を張った後は、保温シートや蓋をこまめに閉めることで、お湯の温度低下を緩やかにし、追い焚きの回数を減らすことができます。
さらに、節水を心がけることも大切です。シャワーを出す時間を1分短縮するだけでも、約10リットルのお湯の節約につながります。
節水タイプのシャワーヘッドに交換するのも、少ない投資で高い効果が期待できる良い方法です。これらの小さな積み重ねが、月々の電気代に違いを生み出します。

契約アンペアと100V・200Vの違いとは
電気温水器の電気代を考える上で、電力契約や設備の仕様について理解を深めておくことも役立ちます。まず、契約アンペアについてですが、これは一度に使える電気の最大量を示すものです。
契約アンペア数が大きいほど基本料金が高くなりますが、電気温水器の「使用電力量(kWh)」に直接影響するわけではありません。
したがって、契約アンペアを下げても、電気温水器の電気代そのものが安くなるわけではない点に注意が必要です。ただし、家庭全体の電気の使い方を見直して契約アンペアを下げられれば、基本料金分の節約は可能です。
次に、電気温水器の電圧には100Vと200Vのタイプがあります。
この違いは、お湯を沸かすパワー、つまり沸き上げ時間に関係します。一般的に200Vのほうがパワーが強く、同じ量のお湯を100Vの約半分の時間で沸かすことができます。
電気代の単価はどちらも同じですが、200Vのほうが素早くお湯を沸かせるため、急な湯切れで日中の高い電気料金の時間帯に沸き増しが必要になった場合でも、短時間で済むというメリットがあります。
ご自宅の電気温水器がどちらのタイプか確認しておくと良いでしょう。

一人暮らしや賃貸物件での対策
一人暮らしの方や賃貸物件にお住まいの場合、電気温水器に関する対策にはいくつかの制約が伴います。
最大の制約は、設備の交換や電力会社との契約変更を自由に行えない点です。電気温水器は物件の設備の一部であるため、勝手に新しい機種に交換することはできません。
故障した場合などを除き、交換を希望する際は、必ず大家さんや管理会社に相談し、許可を得る必要があります。同様に、物件によっては電力会社が指定されており、自由に契約先を選べないケースもあります。
そのため、賃貸物件での対策は、前述したような日々の使い方を工夫する節約が中心となります。
具体的には、お湯の設定温度を季節に合わせて調整する、シャワーの時間を短くする、お湯を使わないときはリモコンの電源を切る、といった方法です。
一人暮らしの場合、お湯を使う量が少ないため、タンクの容量が過剰になっている可能性があります。毎日お湯を沸かすのではなく、2日に1回沸かすといった使い方を試してみるのも一つの手です。
ただし、冬場はお湯が冷めやすいため、湯切れしないよう注意が必要です。自身のライフスタイルに合わせて、無理のない範囲で節約を試みることが大切になります。

古いマンションで注意すべき漏電の兆候
前述の通り、古いマンションの電気温水器は経年劣化による問題が起きやすくなりますが、特に注意すべき漏電の兆候を具体的に知っておくことは、安全と無駄な出費を防ぐ上で非常に大切です。
最も分かりやすい兆候は、漏電ブレーカーが頻繁に作動することです。電気温水器を使用している特定の時間帯や、雨の日などにブレーカーが落ちる場合は、機器本体や関連する配線からの漏電が強く疑われます。
また、以下のような症状も注意が必要です。
・電気温水器本体やその周辺に触れると、ピリピリとした静電気のようなものを感じる
・特別な理由がないのに、先月と比べて電気代が急激に数千円単位で増加した
・本体の金属部分に錆や腐食が目立つ、あるいは周囲が常に濡れている
これらの兆候が見られた場合、放置しておくのは大変危険です。
感電や火災のリスクがあるだけでなく、漏れ出た電気が24時間無駄に消費され続けるため、電気代が異常に高騰する原因となります。
速やかに管理会社や専門の修理業者に連絡し、点検を依頼してください。安全を確保するためにも、早期の対応が鍵となります。

ガス給湯器やエコキュートへの交換費用
電気温水器の電気代があまりにも高い場合、根本的な解決策として給湯器自体の交換を検討する価値があります。主な交換先としては、ガス給湯器と、より省エネ性能の高いエコキュートが挙げられます。
交換にかかる費用の比較
給湯器の交換を考える際、初期費用と長期的なランニングコストの両方を比較することが大切です。
| 給湯器の種類 | 初期費用(工事費込)の目安 | 年間ランニングコストの目安 |
|---|---|---|
| 電気温水器 | 20万円 ~ 40万円 | 約15万円 |
| ガス給湯器 | 15万円 ~ 30万円 | 約8万円 |
| エコキュート | 40万円 ~ 70万円 | 約4万円 |
表から分かるように、エコキュートは初期費用が最も高額ですが、ランニングコストは圧倒的に安く、電気温水器の約4分の1から3分の1程度に抑えられます。
高い初期費用も、長期的に見れば毎月の光熱費の差額で回収できる可能性があります。
国の補助金制度の活用
現在、国は省エネ性能の高い給湯器の普及を促進するため、「給湯省エネ2024事業」などの補助金制度を実施しています。
例えば、基準を満たすエコキュートを導入する場合、2025年度の「給湯省エネ2025事業」では基本額8万円/台で、性能要件を満たすと最大13万円/台まで加算されます。
らに、電気温水器を撤去してエコキュートを設置すると 5万円/台の「撤去加算」が受け取れます。
このような補助金制度を賢く活用することで、エコキュート導入の初期費用負担を大幅に軽減できます。
交換を検討する際は、お住まいの自治体独自の補助金がないかも含めて、最新の情報を工事業者などに確認することをおすすめします。

横浜市の近隣エリアで交換ならお任せ!実際の施工事例をご紹介
「電気温水器やエコキュートの交換、費用は気になるけど、実際にどんな工事になるの?」
「うちのマンションでも本当に設置できる?」
そんな疑問をお持ちの方は、ぜひ弊社の施工事例をご覧ください。写真付きで設置の様子もご確認いただけるため、ご自宅への設置イメージも湧きやすくなります。
電気温水器の電気代が高すぎる悩みの最終手段
- 電気温水器の電気代が高額になるのはヒーターで直接水を温める非効率な仕組みが原因
- 冬は給水温度の低下とタンクからの放熱でさらに電気代が上昇する
- まずは自宅の電気代がエリアや世帯人数の平均と比べて高いか確認する
- 電源のつけっぱなしは自動保温の待機電力と沸かし直しの電力のバランスで考える
- 長期不在時は電源オフが基本だが冬場の凍結には水抜きなどの対策が必要
- 古い機器はスケール付着による効率低下や漏電のリスクがあり電気代を押し上げる
- 従来の安い夜間電力プランが改定・廃止され電気代高騰の大きな要因となっている
- 今日からできる節約術として給湯温度の見直しや節水が有効
- お風呂の自動保温は控えめにし保温シートや蓋を活用する
- 賃貸物件では設備の交換が難しいため日々の使い方での節約が中心となる
- ブレーカーが頻繁に落ちる場合は漏電の可能性を疑い専門業者に点検を依頼する
- 根本的な解決策は省エネ性能の高い給湯器への交換
- エコキュートは初期費用が高いがランニングコストは電気温水器の3分の1以下
- 給湯器の交換を検討する際は初期費用とランニングコストを総合的に比較する
- 国の補助金制度を活用すればエコキュート導入の初期費用を大幅に軽減できる



